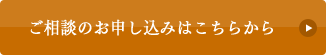離婚コラム
離婚したくない
協力請求
夫婦間の協力義務、配偶者に対する協力請求を、積極的に活用しましょう
公開日:2020.12.03
夫婦間の協力義務、配偶者に対する協力請求って何?
皆さん。夫婦間には、「協力義務」という法的な義務が存在することをご存じですか?
「夫婦なんだから、協力するのは当たり前」といえば当たり前なのですが、実は「協力義務」という、法律上一定の“強制力”をもった義務が存在するのです。
義務である以上、その反面として権利があることになります。つまり、「夫は妻に協力せよ」「妻は夫に協力せよ」と請求することができます。「配偶者に対する協力請求」です。
今回は、判例も存在せず(当事務所が調べた限り)、民法や家族法の教科書等でもあまり解説されることのない「夫婦間の協力義務」、「配偶者に対する協力請求」について、考えてみたいと思います。
民法752条の協力義務
民法752条では、表題として(同居、協力及び扶助の義務)とあり、本文として、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と規定されています。
この条文は、① 同居義務、② 協力義務、③ 扶助義務を定めた規定であると、民法や家族法の基本書等で解説されています。なお、判例上も認められている守操義務(配偶者以外の異性と性的な関係に陥ってはならない義務)も、本条文から導かれると解説されています。
協力義務も法的な義務
いずれにせよ、協力義務は、同居義務や扶助義務などと並ぶ、夫婦間における基本的義務の1つとされています。
れっきとした法的義務ですので、そもそも夫婦間においては裁判所などに申立てをしなくても、配偶者に対して「●●の協力をしなさい」とか、「●●について教えなさい」などと直接請求することができます。
もちろん、求める「●●」の内容が理不尽な要求であれば、配偶者がこれに応じる義務もなく、協力請求できないのは当然です。その夫婦の実情においてあるべき協力義務のあり方を請求する場合にのみ、夫婦間には協力義務があり、配偶者に対する協力請求ができるのです。
そして、配偶者が、あるべき協力義務のあり方について、正当な請求を拒絶したり、無視して応じなかったりした場合、夫婦間における「協力義務」違反の状態になるのです 。
そして、協力義務のあり方(協力請求の内容)に、夫婦間で意見の一致がみられない場合には、家庭裁判所での話し合いである「調停」や、家庭裁判所の裁判官が裁いてくれる「審判(判決のようなもの)」の対象となります(家事事件手続法150条1号参照)。
通常は、先行して協力調停手続が行われ、どうしても話し合いでは妥協点が見いだせない場合に、協力審判手続に移行したうえで、裁判官が何らかの審判を言い渡すことになります。
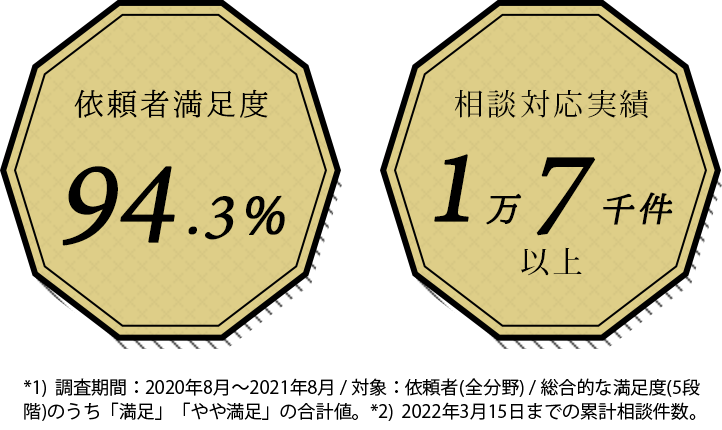
関連記事
・夫婦間の協力義務、配偶者に対する協力請求を、積極的に活用しましょう(本記事)
・家裁統計からみる夫婦間における同居請求、協力請求、扶助請求事件の件数
・夫婦間の協力義務、配偶者に対する協力請求の活用
・協力請求の活用例① -配偶者に対する改善要求-
・協力請求の活用例② -配偶者に対する情報開示請求-
・協力請求の活用例③ -夫婦喧嘩にも裁判を-
・協力請求の活用例④ -卒婚契約への適用-
・協力請求・協力審判の弱点 -強制執行できない!?-
・夫婦間の協力義務違反の効果
・夫婦間の協力義務、配偶者に対する協力請求に関する当事務所の取組み
※本記事は、公開日時点の法律や情報をもとに執筆しております。

【本記事の監修】
弁護士法人桑原法律事務所 弁護士 桑原貴洋(代表/福岡オフィス所長)
- 保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士
- 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。
日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。